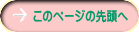6 初代城主は、いつ、どこから?
(2) なぜ、九州から? 三潴左衛門尉のなぞ
初代上関城主とされる
三潴左衛門尉が、九州からはるばる上関の地へ来ることになったのは、いつのことで、どんな理由からか、今となっては全くの謎です。
しかし、当時の時代状況から、来任時期はおそらく文治元年(1185年)に違いないと推測できました。
では、来任の理由や経緯は、どのように推測することが妥当なのでしょうか。
筆者の推測に基づく想像を続けます。
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
桂関に着任して年も明けた春まだ浅き夜、にわか造りの役宅の一室で
左衛門尉と老臣の二人、荒川からあがった鮭の塩引きを肴に盃を交わして、しみじみと思い出話の様子。傍らには、まだ一向に年若い近習の侍が控えている。
「御館様の御最期から、間もなく一年になろうとしておりますな。」
「うむ、我ら三潴一族郎党、こうして北越後の地で何とか命脈を保つことができているとは、一年前には、つゆ思わなんだ。」
「御一族も郎党も、各地に離散し、あわや滅亡かとの瀬戸際で踏ん張りとどまることができましたのは、これ一重に亡き御館様の勇猛果敢な戦いぶりと、京にあって日頃から各地の有力武者たちと信任関係を深めておられた殿の力量ゆえにございます。」
二人は、年若い近習の侍に聞かせるように、これまでのいきさつを語っている。その話をかいつまんで記せば、次のようなことであった。
御館様とは、
左衛門尉の父で筑後三潴荘の荘官を務めた三潴の名族の当主のこと。
三潴氏は九州源平争乱に際し、平氏方として戦った。
三潴勢の戦いぶりは見事で、とりわけ
三潴家当主の勇猛果敢な戦い振りには、さしもの源氏方関東武者も震え上がったものだった。
九州はもともと平氏の地盤で、瀬戸内海を
源義経(みなもとのよしつね)に追い込められていた平氏勢は、九州勢の加勢をあてにしていた。
頼朝(よりとも)は、九州に逃げ込まれては面倒と、壇ノ浦での決戦の前に弟の
範頼(のりより)を九州に攻め込ませ平氏方の武士を掃討させていた。初めは平氏方だった九州在地武士の多くは源氏軍の勢いに恐れ、また源氏軍からの誘いに乗って平氏を見限り、続々と源氏方に寝返った。
そんな中にあって、あくまでも平氏方として戦った
三潴氏であるが、多勢に無勢、武運つたなく敗戦となり、
左衛門尉の父は、
三潴家当主として責任を一身に負い、断罪に処せられた。
三潴家の嫡男であった
左衛門尉は、捕虜として鎌倉へ送られ、
頼朝のもとで蟄居謹慎の身となった。捕虜とはいえ、
左衛門尉の武者ぶりも父に劣らず見事であったこともあって、その扱いは丁寧なものだった。
その上、
左衛門尉は、その官名が示すように、早くから京の宮廷の左衛門府の侍として勤務し、同じように宮廷の侍として勤める当時の有力武家の若武者たちとは常々交流があった。
三潴荘は京の貴族
四条隆季(しじょう・たかすえ)の所領で、荘官を務める
三潴家とは古くから親交を結んでいた。
四条隆季は、
平清盛(たいらのきよもり)の下で平氏政権の高官となっていて、
三潴家にも何かと気を配ってくれていた。
左衛門尉が朝廷から官位を賜り、宮廷の侍として京で暮らすことができたのも
四条家の力が大きく寄与していた。
このような関係もあって、世話になった平氏を無碍に裏切ることはせず、武家としての筋を通した
三潴氏のありようについては、関東武士も一目置いていたし、何よりも、京の武者同士交流があった
左衛門尉の人物力量には、皆敬服の念をもっていた。
このような状況にあったから、いずれ近いうちには、その罪を許し御家人として
左衛門尉を取り立てようと考えている武士たちが鎌倉幕府には大勢いたのだった。
しかし、許しが出るまではあくまでも敗軍の敵将の嫡男として謹慎していたし、一族郎党も各地の縁者を頼って離散し、それぞれの地で敗軍の平氏方として息を潜めて暮らしていたのだった。
まさに罪人として蟄居潜伏(ちっきょ・せんぷく)しなければならない身の上だったのであった。
やがて、九州の戦で直接対戦した
和田義盛(わだのよしもり)の懇請で、
頼朝の許しが出た。それを待っていたのが、越後国司に任じられたばかりの
安田義資(やすだのよしすけ)であった。かつて、ともに京の宮廷侍としてよく知り合っていた仲だった。越後で喫緊の課題となっている国境警備に
左衛門尉の力を貸してほしいと言う。
左衛門尉は、そのことを守役だった腹心の老臣に伝えた。老臣は、
義資の家臣たちと連絡をとり、直ちに準備にかかった。各地に散った一族郎党たちへ手紙を送り、諸準備方を命じたのだった。
一族郎党、蟄居謹慎を解かれたのである。皆、それぞれの地から、遥か遠方をものともせず勇躍して北越後関郷に集結した。と、このような話であった。
「我ら
三潴氏の支族の一つが、三潴荘内高三潴にわずかながら所領を保ち、当地に血脈をつなぐことができたのも、不幸中の幸いであった。」
「さようでございます。古代からの水沼君(みぬまのきみ)につながる名族の血脈が、傍流とは言え、何とか彼の地につながったことは、真に喜ばしいことでございます。」
「うむ、我らはこの北越後の地で、
三潴氏を名乗り、三潴の名族としての誇りを持ち続けようぞ。」
主従三人、固い決意で頷きあって長い語りが終ったとき、中天に月がかかり、役宅の庭の残雪が固く光っていた。
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
九州の名族三潴氏が先祖伝来の地を離れ、遥か遠方北越後関郷の地まで来るからには、相当の事情があったからに違いありません。その事情を生み出したのは、九州における源平の争乱だったと思われます。
 (3) 九州の源平争乱
(3) 九州の源平争乱
平氏を追い詰めた
源頼朝の戦略は、見事なものでした。
文治元年(1185年)1月、四国屋島に籠もった平氏の包囲網を敷くため、
頼朝は、弟
範頼を九州に上陸させ平氏方の有力武将を討たせます。その上で、九州の在地武士たちに、源氏方に付くよう説得工作を行わせました。その間に、
義経が屋島を急襲し、平氏は九州へ逃げようとしますが、そこは既に
範頼に押えられていて、ついに壇ノ浦で滅亡する破目に陥ります。
14歳で伊豆の蛭ヶ小島に配流され34歳で挙兵するまで20年間、関東の片田舎から一歩も出ずに暮らした
頼朝に、どうしてこのような全国的戦略眼が養われたのか不思議です。おそらく、舅の
北条氏をはじめ周囲の関東武士たちは、常に京に行き来していて、西国の事情も含めて様々な情報が
頼朝の下に集まっていたのでしょう。当時の有力武士は、もともと京の下級軍事貴族だったのですから、政治の中心である京には、日頃からしっかりとした足場をもっていたものと考えられています。
それはさておき、
範頼の軍が九州へ向う途中通るのは、すべて平氏の勢力下だった西国でしたから、その苦労は並大抵ではなかったはずです。その上、目指す九州は、平氏の地盤ともいえる地域で、中心地の大宰府は平氏の直轄地でしたから、上陸するのも容易でなく、さらに上陸した後にも平氏方有力武将との戦いが待っていました。
範頼軍はそれらの難題を苦難の末に乗り越えて、平氏方の九州武士を掃討し、多くの在地武士を源氏方につけました。3月の壇ノ浦の決戦では、四国・九州の多くの武士が平氏軍を離れ源氏方に味方したことが源氏に勝利をもたらしたのでした。後世、
義経の戦いぶりだけが有名になっていますが、実は
範頼の働きは大きかったのです。
4月には、
義経が捕虜を連れて京へ戻ります。その後
義経は鎌倉に入ろうとして禁じられ腰越状で有名な兄弟の争いが始ります。それは別にして、捕虜はその後、鎌倉に送られた者もありますし、罪の重い捕虜は京で処刑されました。その際、様々な武士同士のつながりの中で、助命や罰の軽減を求める働きかけが行われました。その頃の武士は、戦のときにはたまたま敵味方に分かれたとしても、日常的には、親戚だったり仲間だったりして互いに深いつながりを持っていました。
特に地方の有力武士は、地方だけで暮らしているのではなく、京でも役目をもっていて、しょっちゅう京と所領のある地方を行き来して生活していました。ですから、敵味方に関わらず、ほとんどの有力武士は顔見知りで、親しく付き合っている者が多かったのです。このような関係の中で、時には敵味方に分かれれば戦いもするけれど、戦いが終れば互いに助け合うということが、武士の社会では普通に行われていたのでした。
三潴左衛門尉も、このような武士のネットワーク社会の中で生きていた人でした。
さて、5月に入ると、
範頼による九州の戦後処理が行われ、平氏方の所領は没収されましたが、当然源氏方についた九州武士は
頼朝の西国御家人となって、それまでの所領が安堵されました。
左衛門尉が、三潴荘に残れなかったということは、西国御家人として所領を安堵されることはなかったということになります。それは、とりもなおさず、源氏方にはつかなかったことを意味しています。
所領を安堵された西国御家人も、ひと時の安泰は得たものの、決して万全ではありませんでした。没収した平氏方の土地には、関東御家人が続々と入ってきて、在地の西国御家人は徐々に圧倒されていったのです。三潴荘にも関東御家人の雄
和田義盛が地頭として補任されます。
源平の争乱後も三潴荘には、
左衛門尉と同じ
三潴氏を名乗る家が残っていましたが、三潴荘の中心部を外れた高三潴という周辺部に所領を確保したようです。おそらく、
三潴氏としては、支族の一部を平氏方に加わらせず、家名の存続を図ったのではないでしょうか。
三潴左衛門尉が桂関に来任することになった背景には、このような、九州の源平争乱があったのでした。だとすれば、北越後関郷の地で、三潴の家名を保つことには、左衛門尉にとって切実な願いであったことでしょう。高三潴に残った三潴氏は、戦国時代には家名を消してしまっています。関郷の三潴氏は、その後四百数十年も、上関城主として家名を保持し続けましたし、その後も絶やすことなく保持し続けています。左衛門尉とその一族郎党の悲願は、見事に果たされたということになるでしょう。